三好京三『俺は先生』
三好京三の『俺は先生』(昭和57年 文藝春秋)を読み、感じたことを書いてみたい。
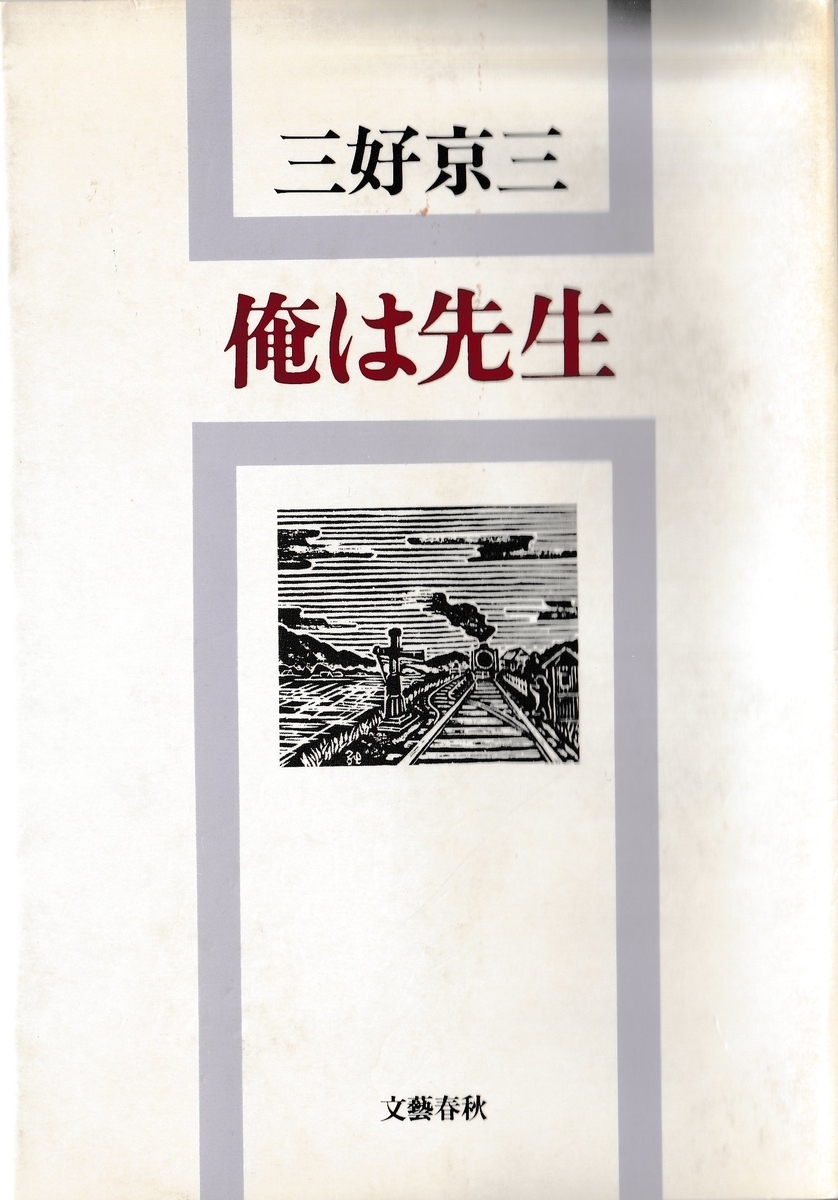
三好京三は昭和6年(1931年)岩手県に生まれ、平成19年(2007年)に亡くなっている。直木賞を受賞した『子育てごっこ』が特に有名である。三好は助教諭として種市町(現洋野町)立の小学校に勤務後、昭和37年(1962年)から衣川村(現奥州市)立衣川小学校大森分校に14年間勤務し、昭和53年(1978年)に教員を辞めて文筆に専念するが、生涯岩手県で暮らしている。
『俺は先生』は「不死身の哲つぁん」と皆から呼ばれる小学校教師・郷内哲也が主人公の小説である。不死身と呼ばれることから想像されるように、哲也はバイタリティーにあふれ、人一倍(私から見れば超人的)教育に熱心でよく働く教師である。(こんな教師は現実的ではないと思われるところが、この小説の欠点かもしれないが、この教師の活動ぶりこそが終戦直後の混乱と活気に満ちた教育状況を教えてくれるようにも思える。)
郷内哲也は昭和22年から国民学校の高等科を出た者たちが通う、村の実業学校の教師として勤務を始める。その後新しい学制がしかれ新制中学ができるが、校舎がないので元の分教場を手直した分室で、中学一年生から三年生まで27人を一人で教えることになる。教員は分室に一人であるから社会、国語、数学、理科、英語、音楽、体育、家庭など全教科を哲也一人で教えるのである。このあたりは終戦後間もない時期の状況が書かれていて実に面白い。
哲也はその後、岩手県北部の僻地の小学校に勤務する。そこで教育こんわ会(教育研究サークル)を作り活動を始める。毎日毎夜子どもの文集、学級だより、教育こんわ会の機関誌などのガリ切りを超人的な精力とスピードでこなしていく。(ガリ切りとはガリ版印刷で原紙に鉄筆で書くことであるが、現在現役の小中高の教員でガリ切りをしたことがある者は皆無と言っていいだろう。私も小中の頃に先生がやっていたのを見て、一二度やったことがある程度である。ガリ切りはパソコンで打つことより、数倍も時間がかかり、労力がいることは言うまでもない。)
子どもの文集は生活綴り方運動の継承から生まれたものだが、当時は学級のほぼ全員が貧乏な家の子であったから、子どもたちは自分の家の生活を見つめ、その貧しさを書いても恥ずかしくなかったのだろう。現在も子どもの7人に1人が貧困状態にあるといわれ、ヤングケアラーなどの問題も顕在化して、貧困の問題はなくなってはいないものの、経済格差の拡大した今、果たして貧しい家の子どもたちは自分の家の実状を隠さずに書くことができるだろうか。書けばいじめや蔑みにもつながりかねない。教員はそのようなプライバシーに関わる作文を書かせることに躊躇するのではないだろうか。私は高校の教員であったが、ほとんど生徒に作文を書かせたことがない。作文を書かせるとしたら現代文の時間だろうが(表現は履修科目にしていない学校が多い)、とにかく授業を先に進めなければならず、作文に割ける時間などなかった。
学級だよりというと、私は昭和60年(1985年)に当時新潟県で最も荒れていると言われていたk高校に赴任したが、k高校の教員の多くが競って学級だよりを毎日のように出していたことが思い出される。教員は学級だよりを卒業の時に製本して生徒に渡していた。その教員たちの熱意には感心させられるばかりであった。しかし私は感心するばかりで自分にはできそうもないと考えて、クラス担任になった時には端からが学級だよりを出すことを諦めた。
教育こんわ会の活動は組合教研につながるものだが、私が昭和60年に新潟県の教員になったころは新潟県の高教組では、支部教研が10月の2学期中間テストの午後に会場は支部内の高校の持ち回りで開催され、そこで選ばれた者が県教研で発表した。そのころからすでに教研はかなり形骸化していたが、それでも最近まで支部教研も開催されていた。今はどうも支部教研はなくなり県教研だけになったようである。組合に加入する者が少なくなり、あまりにも仕事が忙しくなって、教研が成り立たないような状況になっている。
お互いの教員としての成長を促す教研こそ、組合の最重要活動であると思う。組合が組合員であることを理由に不勉強な教員でも助け、教員の生活を守るだけの組織になってはほしくない。
私が『俺は先生』を読んで一番に感じたことは、教員が自由だったということである。教材や教具など全てのものが不足していたが、学校には教員が自分のやりたいと思うことをやれる自由があった。だからこそそこに素晴らしい実践活動が生まれたのである。今の学校は物はそろっていても教員に自由がない。だから活気もない。教員は手に余るほどの仕事を押し付けられて、それをこなすだけで精一杯。その上自由がなければ疲弊するだけである。これをやりたいと思い、それをやれる自由があれば、そこに活気が必ず生まれるはずである。
『俺は先生』は小説である。事実の記録ではない。しかし小説はその時代を背景にして書かれている。だからそこには記録性が備わっている。単なる記録より、小説の方がグッと時代の香りが伝わってくる。記録性は小説の重要な要素である。ぜひ多くの教員や教員を目指す若い人、教育に興味のある人にこの本を読んでほしい。そして今の教育に欠けているものは何かを考えてほしいものである。
最後に『俺は先生』の第九章「かなづかい」は、とても興味深かった。昭和21年に「現代かなづかい」が告示される。(ちょうど40年後の昭和61年には、その改訂版である現行の「現代仮名遣い」が告示される。)「現代かなづかい」は歴史的仮名遣いからの歴史的大変換である。「現代かなづかい」に批判があったことは知っていたが、そのかなづかいが定着するまでに、様々な取り組みがあったことを私は全く知らなかった。これもこの小説が持っている優れた記録性の一例である。